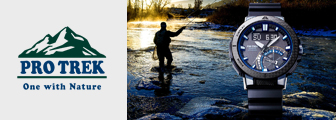-
-
-
ゲスト
ログインして体験したHow Toをレポートしよう!
- NEWS
- 2025.12.08 【イオンモールむさし村山 第9回】「素材からしめ縄作り、オリジナルの正月飾りで新年を迎えよう」
- NEWS
- 2025.12.08 【モリパーク アウトドアヴィレッジ 第8回】「素材からしめ縄作り、オリジナルの正月飾りで新年を迎えよう」
WHAT'S NEW
最新の How To
2025.11.28 UPDATE
-
 房総竹部
1861 views
房総竹部
1861 views近年各地で問題になっている放置竹林。暗く見通しの利かない竹林は獣たちのすみかとなり、そこから夜な夜な獣たちが田畑へと遠征してくるようになっている。ところがほんの数十年前までは、竹林は生活に必要な資源を生み出す宝の山だった。春にはタケノコが生え、その材はさまざまな生活道具の素材に使われてきた。竹林の価値は今も昔も変わらない。変わったのは私たちの手からそれを活用する技術が失われたこと。もう一度竹を生活に生かす技術を身につけて、地域の竹林に息を吹き込んでみよう。
-
 GO!GO!編集部
3720 views
GO!GO!編集部
3720 views日本人なら誰でも一度は拾ったことのあるドングリ。秋の日差しを照り返して光る実はとても魅力的に見えます。もしかしたらドングリに心惹かれるのは、縄文人が食糧にしていたころの記憶が私たちのどこかに残っているからかもしれません。今では食べることの少ないドングリですが、種類を選べばそれほど無理なく料理ができます。近所で拾ったドングリを加工して、先祖たちを養った秋の実りを味わってみましょう。
-
 いぞらど
2222 views
いぞらど
2222 views魚の骨格はバラエティに富んでいて面白いものです。造形そのものの綺麗さカッコ良さはもちろんのこと、じっくり観察するとそれぞれの習性や食性に特化した機能性に気づきます。また、その正反対にまるで説明のつかない不思議さを発見することも……。そんな見れば見るほど興味が尽きない魚の骨格を標本にして残してみましょう。骨格標本の制作にはいくつかの方法がありますが、私が実践するのは魚の形を残したまま、徐肉によって骨格を残す方法です(骨をバラバラにしてあとから組み上げる方法もあります)。手間は少しかかりますが、入門者でも無理なく取り組める方法です。
SPECIAL TOPICS
特集記事
MONTHLY VIEW RANKING
月間ビュー数ランキング!
EVERYONE'S REPORTS
みんなのやった!レポ

身近な水辺で食料を得る!生活技術としての...
2
2
そうだよ
多摩大橋付近

+1
日本のロックバランシング「石花」 アレン...
0
0

魚の骨格標本をつくろう
1
0

野山の植物で繁栄を祈る。天然素材でクリス...
3
0
滋賀県

身近でできる宝探し!川原や海辺でキレイな...
2
1
これ何か分かる人いる...

+1
 山葵
山葵
身近でできる宝探し!川原や海辺でキレイな...
9
1
泥岩だと思う

 ratre
ratre
身近でできる宝探し!川原や海辺でキレイな...
8
2
ratreさんわかる...

 山葵
山葵
身近でできる宝探し!川原や海辺でキレイな...
10
3
どこで見つけた??

 ゼロ
ゼロ
身近でできる宝探し!川原や海辺でキレイな...
7
5
めっちゃ綺麗
ジブリパーク...

+1
野山の植物で繁栄を祈る。天然素材でクリス...
4
1
ご参加いただき、あり...
5,331,223
TOTAL VIEWS ON THE OUR SITE
“自然を観察するがいい。そして自然が示してくれる道を行くがいい。自然は絶えず子どもに試練をあたえる。あらゆる試練によって子どもの体質をきたえる。”
ジャン=ジャック・ルソー
エミール〈上〉 / 今野一雄 訳 / 岩波文庫
THIS TREE SHOWS THE GROWN-UP LEVEL OF YOUR WILD MIND.
この木は現在のあなたの「ワイルドマインド」成長段階を表しています。
GROW YOUR WILD MIND!

















 藤原祥弘
藤原祥弘







 宮原 悠
宮原 悠





 柴山元彦
柴山元彦





 三森 典彰
三森 典彰