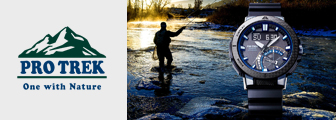-
-
-
ゲスト
ログインして体験したHow Toをレポートしよう!
- NEWS
- 2025.12.26 『自然の解像度をアップ!はじめての「野外活動用双眼鏡」を選ぶ』を公開しました
- NEWS
- 2025.12.22 「WILD MIND GO! GO!」体験イベント2025【第8回】昭島アウトドアヴィレジ「素材からしめ縄を作り、オリジナルの正月飾りで新年を迎えよう」を開催しました!
WHAT'S NEW
最新の How To
-
 宮原 悠
1282 views
宮原 悠
1282 views山遊び、自然観察、狩猟、冒険。どんな野外活動であっても、「もう少し遠くの様子を、はっきり確認したい」と感じる場面があります。風景の奥行き、木立の向こうの動き、見慣れない動植物。そうした視覚情報を補ってくれるのが双眼鏡です。 双眼鏡は、特別な観察をするための専門道具と思われがちですが、実際には自然遊びそのものの解像度を高めてくれる、ごく実用的な道具です。遠くを見るというよりも、「これまで曖昧だったものが、意味のある情報として見えるようになる」。その変化は、野外での判断や安心感にもつながります。 一方で、いざ双眼鏡を選ぼうとすると、倍率や口径、構造、コーティングなどの専門用語が並び、最初の一歩で迷ってしまう人も少なくありません。本稿では性能比較に踏み込みすぎることなく、「野遊びに双眼鏡を持っていく」という行為を無理なく始めるための選び方を整理していきます。
-
 トミザワタクヤ
2692 views
トミザワタクヤ
2692 views人は植物や昆虫、獣から糸を取って利用してきました。細く長い1本の糸を、広がりのある布にするのが織りと編みの技術。糸を縦横に組み合わせてはじめて、布として利用できるようになります。織りの技術のなかでも最もシンプルなのが平織りです。経糸と緯糸を交互に織るこの方法で、布の原点を感じてみましょう。布や洋服はすべて、糸の集合体ということを感じられます。
-
 房総竹部
2157 views
房総竹部
2157 views近年各地で問題になっている放置竹林。暗く見通しの利かない竹林は獣たちのすみかとなり、そこから夜な夜な獣たちが田畑へと遠征してくるようになっている。ところがほんの数十年前までは、竹林は生活に必要な資源を生み出す宝の山だった。春にはタケノコが生え、その材はさまざまな生活道具の素材に使われてきた。竹林の価値は今も昔も変わらない。変わったのは私たちの手からそれを活用する技術が失われたこと。もう一度竹を生活に生かす技術を身につけて、地域の竹林に息を吹き込んでみよう。
SPECIAL TOPICS
特集記事
MONTHLY VIEW RANKING
月間ビュー数ランキング!
EVERYONE'S REPORTS
みんなのやった!レポ

 おとしふみこ
おとしふみこ

 sanamaruko
sanamaruko


 どらやき
どらやき

 くま
くま




 ごんし
ごんし

“耳に聞こえるメロディは美しい。しかし聞こえないメロディはもっと美しい。”

















 三森 典彰
三森 典彰











 藤原祥弘
藤原祥弘







 柴山元彦
柴山元彦